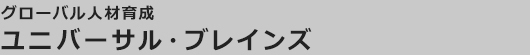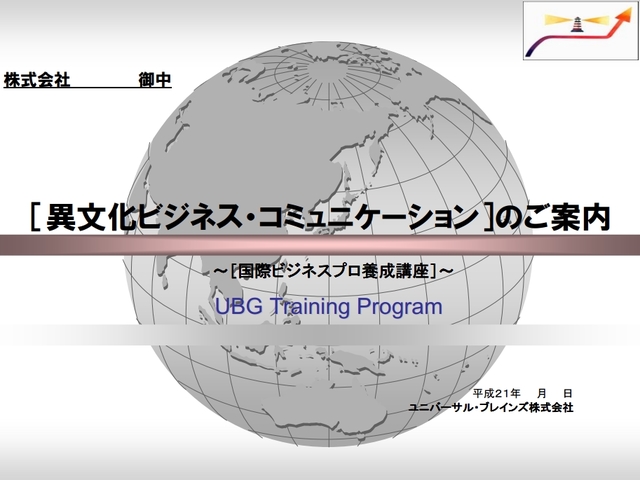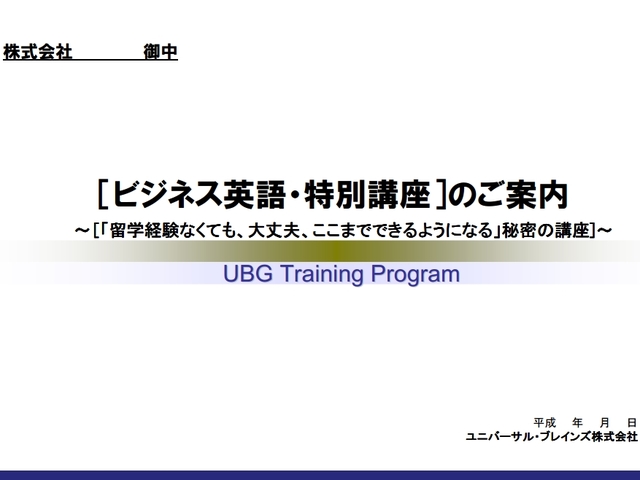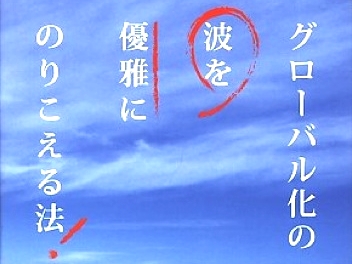各企業‐グローバル人材育成の現状
日本企業のグローバル化のために、かつてはごく一部の社員だけをMBAに送り込んで「国際化」する施策が一時流行しました。
しかし、その後多くの中堅社員がみずからグローバル化の先頭にたたなくてはならなくなりました。
インターカルチャー(異文化コミュニケーション力)を高め、グローバル・リーダーシップを身に着けることが、今、最も求められています。それは単なる英語力を高めることではありません。
日本のグローバル企業のグローバル化の最前線の報告をご紹介します。
大成建設のグローバル人材育成 |
大成建設、入社後すぐに海外研修—新人育成、新興国から(11月1日 日経新聞) |
大成建設は今年度から入社したての新人をいきなり海外の現場に送り込む研修を始めた。派遣先はトルコ、カタールなど。日本の大手総合建設会社(ゼネコン)はここ数年で国際化が進み、海外企業と共同企業体(JV)を組む機会も増えた。日本とは全く違う環境にいきなり放り込む荒療治でグローバル人材の早期育成を狙っている。
「こんなに早く海外の現場に出られるとは思いませんでした」。新入社員の竹中将洋さん(23)は、8月末までトルコ・イスタンブールのボスポラス海峡トンネル工事の現場で研修を受けた。 「必要な資材を現地に輸入する際の通関手続きなど、交渉の難しさ、厳しさに気がついた」(竹中さん)。 同じころ、松久保恵利子さん(23)はカタールの首都ドーハにいた。空港ターミナルビルの建設現場で研修を受け、施主との契約や資材調達などの実務を中心に手伝った。事務だけでなく、工事現場にも4週間ほど通った。建築現場の気温は朝6時で既に40度を超え、湿度は80%近い。未体験の環境を味わった。
「日本と同じレベルの安全意識を現地の労働者に持ってもらうにはどうしたらいいか」。現場に足を運んだ松久保さんは、海外での労務管理の難しさを考えるようになったという。
英国留学の経験がある松久保さんは、カタールでは自慢の英語が通用しない経験もした。「現地の人たちはアラビア語の単語や慣用句を取り入れた英語を話すので一筋縄ではいかない」。国によって異なる英語表現の多様性を知った。
竹中さんと松久保さんは現地でイスラム教の断食「ラマダン」も経験した。この時期にはオフィス内での食事は厳禁。日本人や欧米人が昼食を取るときは、食堂にカーテンが張られた。
竹中さんは「(ラマダン中は)暑さと断食で労働者が脱水症状になりやすい。そんなことはまったく知らなかった」と語る。異なる宗教・文化を持つ国の現場では仕事の進め方も現地に配慮しなければならない。 今年は5月から8月にかけ、竹中さんや松久保さんを加え新入社員7人がアジア、中近東のインフラ建設現場に派遣された。「海外に転勤したときに短期間で現地に溶け込めるよう社員を訓練しておく必要性が高まっている」(人事部)からだ。
大成建設など大手ゼネコンの主戦場は、国内から海外へ移りつつある。ライバルの韓国・中国企業も海外で受注を増やしており、対抗するには海外即戦力の育成が不可欠だ。
同社は2年前から日本に留学する外国人を対象とした新卒採用を始め、今年4月には中国人とシリア人の合計3人が入社した。海外現地法人での新卒採用はまだ取り組んでいないが、「日本語の会話能力が高いなど条件を備える人から申し込みがあれば検討したい」(同)という。
日本人の新人については、これまで国内で5年以上、実務経験を積んでから海外研修を受けさせていたが、それでは人材育成が追いつかないと見て、入社していきなりの海外研修に踏み切った。
海外で汗を流す先輩たちの姿を見てきた竹中さんたちは、帰国後も高い目的意識を持って仕事に取り組んでいるようだ。
経済産業省の海外事業活動基本調査によると、2008年度末時点で日本企業の海外法人数は前年比5・5%増の1万7658社。アジアが7・5%増と全体を上回る伸び率になった。
生産の海外移転を進める製造業や海外進出する非製造業が増えており、海外現法は毎年増加している。特に高い経済成長が続く中近東やアジア地域での増加が目立つ。
企業は現地で即戦力となる人材の育成強化が課題。現地の習慣や文化に慣れさせるため、早い段階から海外研修を実施する企業も増えている。 |
今や、MBAのような少数エリートに頼ることなく、社員全員のグローバル対応力を育成する必要があるのです。
そのためには、社員全員のマインドセットとアティテュード、そしてスキルアップの3点セットが必要です。
特に、前2者は異文化コミュニケーション力です。日本人の良さを生かしながら、違いをうまくコントロールする「異文化コミュニケーション力」がキーになります。