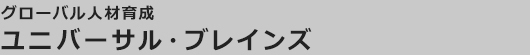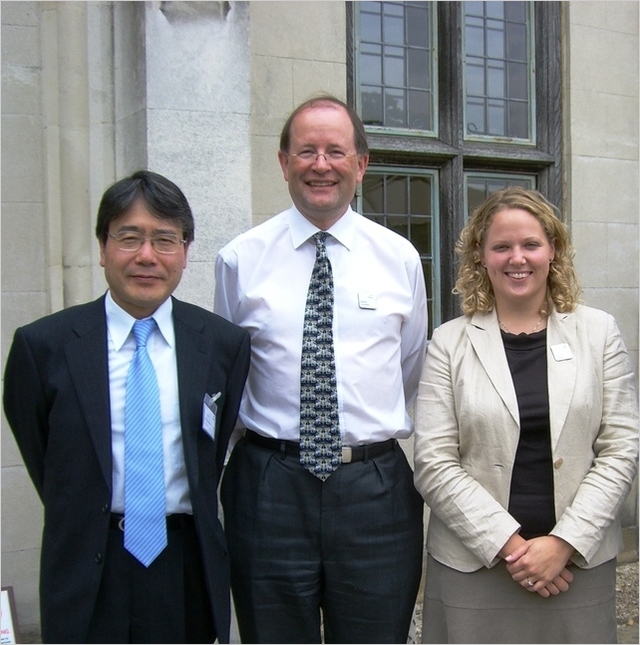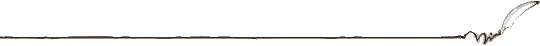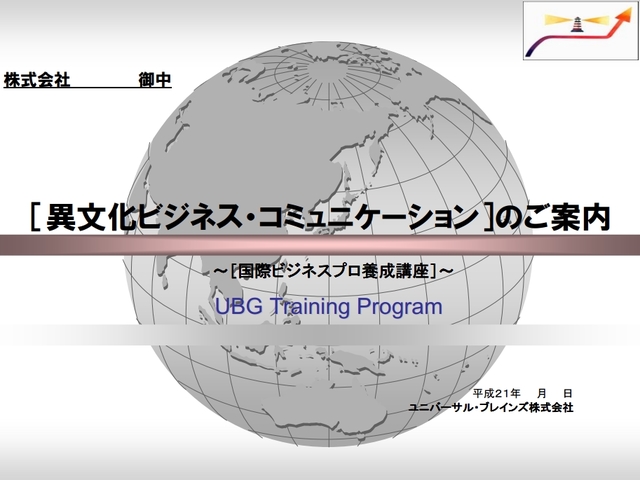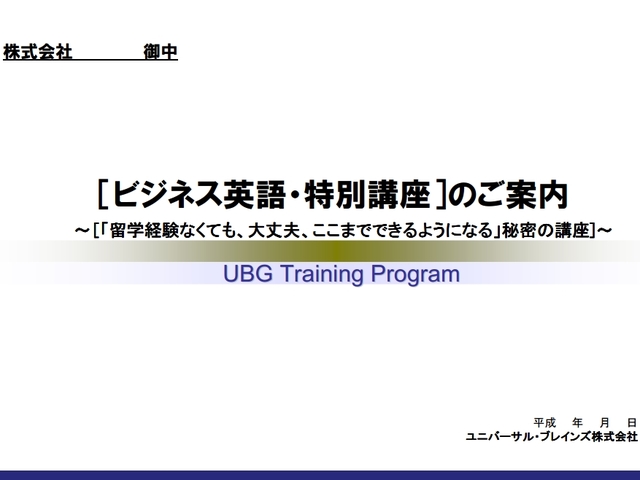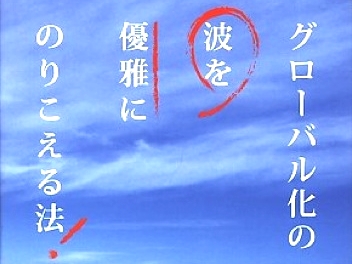グローバル人材育成プログラムとは、グローバル化をめざす日本の上場・中堅企業を、グローバル化に特化した社内研修を行うことで、支援する総合的なプログラムのことです。
グローバル人材育成プログラムは、貴社の実情と要請に合わせて、自由にコンポーネントを組み合わせることが出来ます。
どのようなグローバル人材育成プログラムのコンポーネントがあるのでしょうか。
当社のサービスをご説明します。
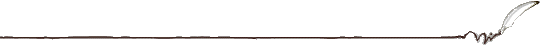
(1)グローバルに活躍できるスキルを総合的に身につける人材教育コンポーネント
「異文化コミュニケーション」コンポーネントは、リーダーシップやチームワークのスキル以上に特別に訓練の必要な項目です。
違う国籍、違う考え方、違う人間とのコミュニケーションをとるためのフレームワークを身につけます。しかし、日本ではこの点の学校教育はなされず、ビジネス現場でも意識されていません。これには特別のトレーニングが必要なのです。
弊社のグローバル人材育成プログラムの強みは、異文化コミュニケーションのフレームワークを身につけるトレーニングが出来ることです。海外ではこうするのです・・・という平板的断片的な知識は無用です。
どのような困った事態・ストレスのたまる状況であってもそれを巧くマネージするロジカルなアプローチが重要なのです。当社のワークショップは、学問的に実証された方法論を用います。しかしアカデミックすぎず、かつ実際に即運用できることが強みです。和の世界で以心伝心になじんだ日本人にとっては「強い自立した個人」を作り、修羅場をくぐりぬけ、よりよい人間関係を築け上げる基本プログラムなのです。
実際に上場企業で、当社の異文化コミュニケーション実践研修プログラムが採用され大きな実績を得ています。詳しくは・・・
また、このカテゴリーの研修で、もっともユニークでパワフル、役に立つ社内セミナーがコミュニケーション・ワークショップです。職場のコミュニケーション力を高め、チームビルディングや問題解決、リーダーシップ養成に役立ちます。
(具体的手法等は、短時間で要点をお知らせできるエレベータピッチセッションをご利用ください。)「スキルとしてのビジネス英語実践研修」コンポーネント。
いうまでもなく英語はグローバルビジネスにとって必須ですが、グローバルの人材としてはネイティブ英語である必要は全くありません。
ビジネスを成功に導くという「目的」に合わせて、状況に応じたコミュニケーションのできる「インターナショナル・イングリッシュ」を身につけることがゴールです。この「状況対応」という点と異文化コミュニケーションのロジックを背景にしていることが他社にない当社独自のビジネス英語実践研修の強みです。
詳しくは・・・ たとえば英語ミーティングとプレゼンテーションスキルについてはこちら。
「財務の基本知識習得研修」コンポーネント。
日本人中堅ビジネスパーソンがグローバルの人材として活躍するときに一番の弱みは、ファイナンスとアカウンティング等の「財務の基本知識」を身につけていない点です。その弱点克服のためにMBAの基本であるファイナンスとアカウンティング(財務会計と管理会計)の知識を重点的に身につけます。
現地法人による日本本社財務報告、現地での相手企業の財務分析等にすぐに役立つ現地トップマネジメントとして必須のスキルです。基本に絞り込み、数値の意味と操作を中心にアカウンティングの基本を、グローバル会計に強い会計士プロフェッショナルが、日本で集中的に社内研修します。
詳しくは・・・財務の基本知識社内研修についてはこちら。「社内ミニMABAコース」は、これらの総合コンポーネントです。
オペレーションマネジメント・マーケティング・事業戦略等のMBA基本8科目を学んでおくことは、グローバルの人材の基本です。欧米での教育を受けた現地ローカル人材やプロセスをマネージするために役立つ必要なスキルです。
これらの総合的な知識とスキルは、コミュニケーションの前提としての「強い自立した個人」として日本人ビジネスパーソンが議論に強くなる基本中の基本です。ここでも他社と異なり、通常は組み込まれていない、強い個の確立とコミュニケーション力を増強する「異文化コミュニケーション」科目が中核になるところに当社の社内ミニMBAコース独自性・強みがあります。
詳しくは・・・
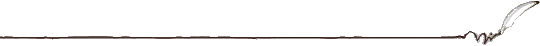
海外赴任前研修を行います。日本企業には海外拠点で働ける中堅幹部候補が足りないのです。しかも、実際上現に海外駐在している海外要員・駐在・派遣者は、十分の訓練を経た上で派遣されているとは限りません。
しかし、現地の業務に影響を与えずに短時間で、現地で、「後から知識・スキル」としてさらに効果的に身につけることができます。すでに海外に滞在し異文化環境下にあるだけに切実にしかし効果的にグローバル要員の実力アップをサポートできるのです。
どのようなサポートを行えるのでしょうか。それを以下に説明します。
現地で「異文化コミュニケーション」のスキルをフレームワークとして身につけるワークショップ(双方向)研修を実施します。
違和感を感じる問題点の新たな再整理と具体的な問題解決につながります。
A-ha体験により日本にいるときよりも現実問題を即解決できるメリットがあります。
現地でのグローバル人材養成・研修です。
たとえば、シンガポール現地法人での研修実例についてはこちら。
中国・上海での現地外国法人での研修(日本事業プロジェクト)についてはこちら。「異文化職場のコミュニケーション」のスキルをワークショップ研修します。
これは既に現地で活躍中の駐在員の外国職場での対人関係の悩みを体系的に解決することができます。
しかもこの職場のコミュニケーションスキルを身につけることで問題解決を直接やってみたり職場の危機的状況を回避する強い人間関係構築のスキルを実践したりできます。
外国の職場にいることでそのメリットを即実感できます。
外国ではこのようなコミュニケーションワークショップは頻繁に実施されスキルアップしているのに、日本のグローバル企業ではハイコンテクストな(以心伝心)企業文化がゆえに実施されていない弱点があります。
その弱点を克服し強みに変える画期的なインパクトの強いワークショップ研修です。
「強い自立した個人」とそのコミュニケーションスキルを、ドイツとアメリカで発展させた独自のトレーニング手法を用います(「気づきの輪」)。
現場に強いファシリテーターを当社社長自身が務めるのが鍵です。
「海外拠点・要員の危機管理セミナー」。
これは単に技術的対応にとどまらず、経営マネジメントの観点から危機管理を捉えなおす画期的な社内研修です。欧米グローバル企業の危機管理の本質と対応を現場での体験に基づきレクチャーし、貴社の危機管理態勢と比較します。
その比較自体を「異文化職場のコミュニケーション」のスキルを実際に使いながら具体的なアクションプランに結び付けるため、非常に効果がある現地社内研修です。
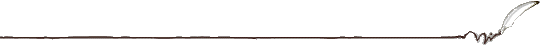
(3) 「将来の海外法人社長・CFO/COO」の育成プログラム。
これは、欧米MBAのコースに留学させるだけでは、離職などにより員数的に不足する現状を変え、次期現法社長等を育成するための「有能人材プール」をしっかりと社内に構築することが目的です。
具体的には、次期候補者に対し、ハイレベルインターンとして欧米有力企業に直接その職場に送り込み、当該グローバル企業の社内コミュニケーションのありかた、意思決定のありかたなどを現場で経験する、という貴重な体験をつむことにあります。
これはハイフライヤーあるいはハイポテンシャルと呼ばれる次期候補者養成のもので、通常のインターンとは全く趣旨が異なります。
しかし、実現は容易ではありません。たとえ貴社と業務提携関係になくとも有力欧米企業と互恵関係を結ぶことで、同業・異業種の企業との人材交流が可能となるのです。
当社独自に欧米大学とのスポンサー提携を仕掛ける「将来の海外法人社長・CFO/COOの育成プログラム」です。実際に上場会社で初めてとなるこの機能が今年いよいよ始動します。
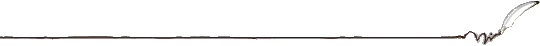
(4) 日本本社での外国籍社員、外国人新卒者向けの「ケミストリー(融合)プログラム」
今や新卒採用者の30%を外国人が占める企業も多くなり、日本の大手金融機関では全社員の5人に一人が外国人となっているのが現実です。
その場合の外国人は日本語も話せるので語学の問題よりは、そこでは「職場での異文化コミュニケーション」が大きな課題になっています。
そこでは外国人・日本人上司がペアになり、具体的な問題解決を一緒にしていく中で、コミュニケーションの基本フレームワークを実践として使いこむトレーニングをします。
ワークショップの時間内だけの融合による有益な結果ではなく、スキルを共有することで、中長期的に外国人社員も日本人上司も共にケミストリーの実を得て信頼感を醸成することができるという一石二鳥を図れます。
また単に融合をはかるだけでなく、ダイバーシティ(人材多様化)によるイノベーション効果を狙うのがゴールです。
人事部としてはリスクを感じるかもしれませんが、実際に上場企業での実践により、大きな成功を収めている実績があります。
研修委託基本契約書の手交
- 支払方法、緊急時連絡方法、キャンセル規定等を事前に取り決めておきます。
- 個別の研修ごとに研修要領を個別契約書により実施いたします。これは個別見積によります。特別目的の場合は、内容の作りこみのための制作費がかかる場合があります。)
- 研修終了後のフィードバックを行います。(無償)
個別相談会
当社では、上記のどのコンポーネントが貴社の実情と必要性を満たせるか、真に有効かの個別のご相談に応じます。
それが「エレベータピッチ・セッション」と呼ばれる個別相談会です。
(この意味は、エレベータで上下する間に肝心の話ができるくらいにコンサイスに要約してポイントをつかむことのできる相談会という意味です)。
このエレベータピッチ・セッションの目的は、短時間に手短に貴社のニーズを分析することです。
そして実際にどのような形での研修になるのか、そのコア部分の一部を実体験していただき、効果を納得していただきつつ、ご一緒に計画を策定します。
グローバル化を推し進める日本企業において、「グローバル人材育成」の施策は最重要の経営課題となっています。
今、各企業では、どのような「グローバル人材育成」のための施策を打っているのでしょうか。
その事例を最近の新聞記事からご紹介します。
神戸製鋼のグローバル人材育成 |
| 海外駐在経験、800人に倍増、神戸製鋼、20年まで。(11月8日 日経新聞) |
20年までに海外売上高比率を現在の3割から5割に高める経営方針に沿って、人材育成を急ぐ。 入社6〜12年目の係長クラスを営業や経理の支援といった名目で海外支店などに定員とは別枠で送り込み、経験を積ませる。神戸製鋼本体の総合職に占める海外駐在経験者の割合は、現在の1割から2割に高まる。 収益に責任を持つ各事業部門は、コスト増加につながる駐在員の増強には消極的だった。海外要員の一部人件費は事業部門の代わりに人事労政部が負担するようにして、事業部門の負担を減らす。 神戸製鋼は海外生産や輸出の拡大により、5〜10年後に連結売上高を08年度より9000億円多い3兆円とする経営計画を打ち出している。海外事業を拡大するための人材育成を急ぐ。 |
ただ若手社員の海外派遣や駐在員政策だけでは今や意味を持たなくなっています。先輩・後輩でつなげていく以心伝心の心得だけでも不足です。
また、理論面だけの座学だけでも実践的とはいえません。
当社では、双方向コミュニケーションのワークショップ方式で、異文化コミュニケーションのフレームワークを実践的に学びます。
日本企業の中でも、国際的活動の幅広さとその歴史にかけては総合商社の右に出るものはないかもしれません。
しかし、それでも、しっかりとした体系的な人材育成策をとるようになってきたのはごく最近のことです。
そして、そこでは、とくに当然のことと思われ、いまさらと思われるような基本的なインターカルチャーに対する基本認識を体系的に身に着ける機会はなかなかないのが現状です。
日本の総合商社における「グローバル人材育成」に関する記事をご紹介します。
三菱商事、丸紅、伊藤忠のグローバル人材育成策 |
三菱商事や丸紅、来春から、20代全社員に海外経験、グローバル人材を育成(11月22日日本経済新聞) |
三菱商事、丸紅など大手商社は来年春、20代の全社員に海外経験を義務付ける新制度を導入する。
三菱商事は現行の語学・実務研修などを「グローバル研修生」と呼ぶ制度に統合する。
丸紅も来年度から、駐在や語学研修、実務研修などで海外に送る若手人員を年30人以上に増やす。
すでに若手全員を対象に4カ月以上の海外英語研修を実施している伊藤忠商事は、来春入社の新入社員から全員に中国での語学研修を義務化する方針だ。
商社の業績は資源高などを追い風に好調だが、今後の売り上げや利益の大半は海外に依存する見通し。
企業の研修事情に詳しい日本能率協会の村橋健司教育・研修事業副ユニット長は「今は会社全員でグローバル化に取り組むのが特徴。 |
丸紅株式会社におかれましては、昨年(2011年度)の若手管理職研修として、弊社ユニバーサル・ブレインズの「異文化コミュニケーション研修」と「職場のコミュニケーション」研修が、ワークショップ形式で、2回行われました。
日本企業のグローバル化のために、かつてはごく一部の社員だけをMBAに送り込んで「国際化」する施策が一時流行しました。
しかし、その後多くの中堅社員がみずからグローバル化の先頭にたたなくてはならなくなりました。
インターカルチャー(異文化コミュニケーション力)を高め、グローバル・リーダーシップを身に着けることが、今、最も求められています。それは単なる英語力を高めることではありません。
日本のグローバル企業のグローバル化の最前線の報告をご紹介します。
大成建設のグローバル人材育成 |
大成建設、入社後すぐに海外研修—新人育成、新興国から(11月1日 日経新聞) |
大成建設は今年度から入社したての新人をいきなり海外の現場に送り込む研修を始めた。派遣先はトルコ、カタールなど。日本の大手総合建設会社(ゼネコン)はここ数年で国際化が進み、海外企業と共同企業体(JV)を組む機会も増えた。日本とは全く違う環境にいきなり放り込む荒療治でグローバル人材の早期育成を狙っている。
「こんなに早く海外の現場に出られるとは思いませんでした」。新入社員の竹中将洋さん(23)は、8月末までトルコ・イスタンブールのボスポラス海峡トンネル工事の現場で研修を受けた。 「必要な資材を現地に輸入する際の通関手続きなど、交渉の難しさ、厳しさに気がついた」(竹中さん)。 同じころ、松久保恵利子さん(23)はカタールの首都ドーハにいた。空港ターミナルビルの建設現場で研修を受け、施主との契約や資材調達などの実務を中心に手伝った。事務だけでなく、工事現場にも4週間ほど通った。建築現場の気温は朝6時で既に40度を超え、湿度は80%近い。未体験の環境を味わった。
「日本と同じレベルの安全意識を現地の労働者に持ってもらうにはどうしたらいいか」。現場に足を運んだ松久保さんは、海外での労務管理の難しさを考えるようになったという。
英国留学の経験がある松久保さんは、カタールでは自慢の英語が通用しない経験もした。「現地の人たちはアラビア語の単語や慣用句を取り入れた英語を話すので一筋縄ではいかない」。国によって異なる英語表現の多様性を知った。
竹中さんと松久保さんは現地でイスラム教の断食「ラマダン」も経験した。この時期にはオフィス内での食事は厳禁。日本人や欧米人が昼食を取るときは、食堂にカーテンが張られた。
竹中さんは「(ラマダン中は)暑さと断食で労働者が脱水症状になりやすい。そんなことはまったく知らなかった」と語る。異なる宗教・文化を持つ国の現場では仕事の進め方も現地に配慮しなければならない。 今年は5月から8月にかけ、竹中さんや松久保さんを加え新入社員7人がアジア、中近東のインフラ建設現場に派遣された。「海外に転勤したときに短期間で現地に溶け込めるよう社員を訓練しておく必要性が高まっている」(人事部)からだ。
大成建設など大手ゼネコンの主戦場は、国内から海外へ移りつつある。ライバルの韓国・中国企業も海外で受注を増やしており、対抗するには海外即戦力の育成が不可欠だ。
同社は2年前から日本に留学する外国人を対象とした新卒採用を始め、今年4月には中国人とシリア人の合計3人が入社した。海外現地法人での新卒採用はまだ取り組んでいないが、「日本語の会話能力が高いなど条件を備える人から申し込みがあれば検討したい」(同)という。
日本人の新人については、これまで国内で5年以上、実務経験を積んでから海外研修を受けさせていたが、それでは人材育成が追いつかないと見て、入社していきなりの海外研修に踏み切った。
海外で汗を流す先輩たちの姿を見てきた竹中さんたちは、帰国後も高い目的意識を持って仕事に取り組んでいるようだ。
経済産業省の海外事業活動基本調査によると、2008年度末時点で日本企業の海外法人数は前年比5・5%増の1万7658社。アジアが7・5%増と全体を上回る伸び率になった。
生産の海外移転を進める製造業や海外進出する非製造業が増えており、海外現法は毎年増加している。特に高い経済成長が続く中近東やアジア地域での増加が目立つ。
企業は現地で即戦力となる人材の育成強化が課題。現地の習慣や文化に慣れさせるため、早い段階から海外研修を実施する企業も増えている。 |
今や、MBAのような少数エリートに頼ることなく、社員全員のグローバル対応力を育成する必要があるのです。
そのためには、社員全員のマインドセットとアティテュード、そしてスキルアップの3点セットが必要です。
特に、前2者は異文化コミュニケーション力です。日本人の良さを生かしながら、違いをうまくコントロールする「異文化コミュニケーション力」がキーになります。
グローバル人材育成には、日本人社員のグローバル化のほかに、外国籍社員の育成が課題となります。
日本のグローバル企業の先兵である総合商社のケースについて事例紹介しましょう。
三井物産のグローバル人材育成=外国籍社員の育成策 |
三井物産、外国籍幹部登用へ新制度 ハーバード大などと(1月19日 日本経済新聞) |
三井物産は外国籍社員登用のため、新たな人事・研修制度を導入する。
来年度に導入する幹部候補育成研修は、欧米の有名ビジネススクールと三井物産が独自カリキュラムを策定する。
対象は30代半ばから40代半ばの中堅社員で、現地採用の外国人と本体の日本人から年約30人選ぶ。
海外人材登用へ採用も見直す。アジアなど海外の大学新卒採用を現在の年25人から順次増やすほか、来年10月をめどに法務や税務などの専門職や高度な経営人材を年俸数千万円以上で処遇する採用枠も新設する方針。 三井物産では、本社採用社員の6136人に対し、現地採用の外国人は約半分を占めるが外国人幹部はほとんどいない。 新制度導入で海外人材の育成と日本人社員の活性化を図る狙いがある。 |
ここでもおそらく外国人社員の高度なスキルセットだけでは、同社社員としてのマインドセットを共通にすることはかなり難しいことかもしれません。
外国籍社員にとっても日本人とその組織論的な深い理解をもつ必要があるのです。
外国籍社員にも、異文化コミュニケーションのフレームワークをロジカルな説明でよく理解してもらうことが肝要でしょう。
それを日本人社員と一緒にワークショップすることがなお一層効果的になるのです。
三菱商事のグローバル人材育成策 「外国籍社員の登用」 |
三菱商事、外国籍社員、幹部に登用—日本流、丸の内で学ぶ(追跡この改革)(7月5日 日本経済新聞) |
三菱商事が外国籍社員の幹部登用に動き出した。
|
三菱商事のグローバル人材育成策にみられるようなGLPつまり外国人を含む幹部候補生のワークショップを集中的に行うケースは、実は世界のグローバル企業ではごく普通に行われている育成策といえます。
今後の課題としては、そのワークショップの内容になっていくと思われます。
たとえば、今まで考えたことのないような(答えの見つからない)問題に対してどのようにアクションをおこすのか、考え方の違う人どうしでどのように合意を短時間で作り上げるか、チームアップのしかた、リーダーシップのとりかた・・・など人間力を鍛え育てる部分が中核になっていきます。
それはMBAのような経営的なスキル一辺倒ではない、ということが最近の世界的なグローバル企業における先端的な育成策になっているといえます。
また、「グローバル人材プール」の策定とそのメンテナンス・アップデートも、グローバル企業におけるグローバル人材育成策のプラットフォームになっています。
この点も、見逃せない特徴です。
日本の製造業におけるグローバル人材育成策について、ご紹介をします。
味の素におけるグローバル人材育成策 |
味の素が研修制度、海外採用社員、幹部に育成、欧米やアジア、30代対象(9月7日 日経新聞) |
味の素は海外子会社の現地採用社員を経営幹部に育成するための研修をスタートする。
新たに始めるのは「リージョナルトレーニングプログラム」。
研修では、グループ戦略への理解を深めてもらうと同時に、味の素が求めるリーダー像や日本を含めた異文化への接し方なども学んでもらう。
味の素は世界で2万人の社員を抱え、調味料や加工食品、飼料用アミノ酸などを製造・販売する子会社を各地に設けている。
これまで専門的な研修は実施してきたが、グループ全体について学ぶ機会はあまり設けてこなかったという。
現在、約70社ある海外現地法人に部長級以上の経営幹部ポストは約210あるが、日本人以外が就いているのは約70にとどまる。 |
各企業のグローバル人材育成策
日本のグローバル企業のグローバル人材育成策の例をご紹介しましょう。
日清食品ホールディングスのグローバル人材育成策 |
若手社員に海外研修制度/日清食品HD、来春導入へ |
日清食品ホールディングスは8月25日、国内実務経験を積み一定の語学力がある入社5年目までの若手社員を対象に、海外の現地法人で2年間の研修を経験させる人事制度を来年3月から導入すると発表した。 アジアなど新興国を中心に成長が見込める海外市場で次世代の幹部候補を育成するのが狙い。 対象となるのは、3年間の国内実務経験があり、英語能力試験「TOEIC」730点か中国語検定試験「HSK」6級を満たした、入社5年目までの全社員。
安藤宏基社長は「柔軟性や行動力がある若いうちに異文化を理解する姿勢を身に着けることが大切。 |