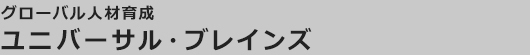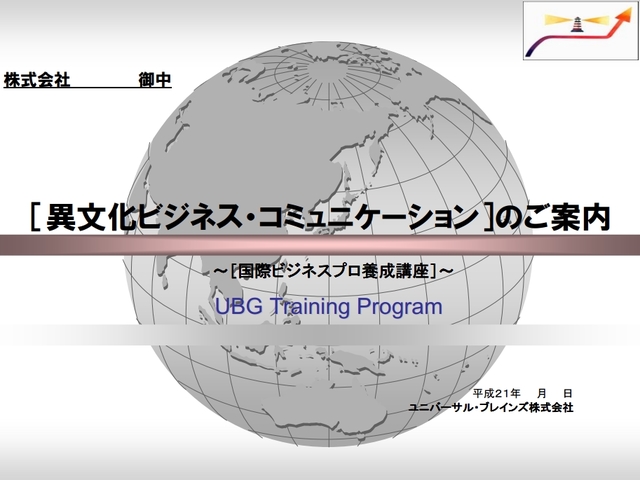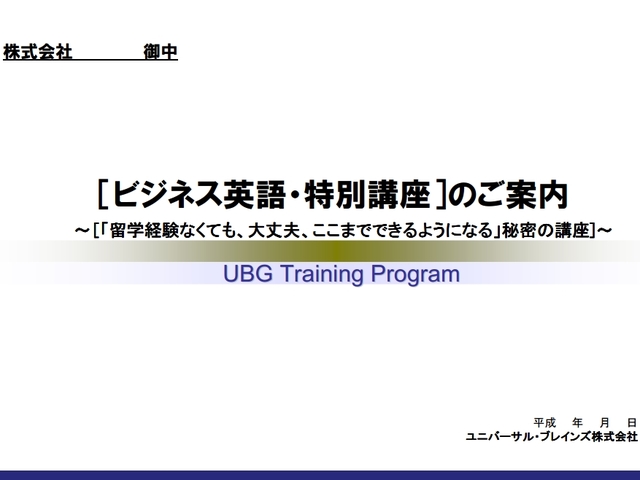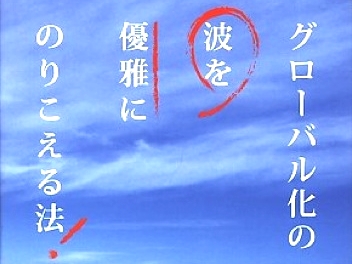「インターナショナル・イングリッシュ」
(吉田研作教授の見解)について
「インターナショナル・イングリッシュ」という言葉はあまり聞きなれないかもしれませんが、上智大学の吉田研作教授(上智大学外国語学部英語学科)が紹介されている動画があります。JIIの2009年度のコンフェレンスでも同趣旨の講義がありました。
ネイティブも含む多国籍の人達が喋るときに、生まれるべき英語がインターナショナル英語だということです。
アメリカ英語とか、イギリス英語にこだわるのではなくて、国際的に通じえる英語というのが理想ではないか。
日本人が、アメリカ人のネイティブの会話を分からなくてもやむをえないので、国際的に理解できる英語を確立したらいいというみたいな感じです。
そして、吉田先生が言っているのは、日本で英語を教えているアメリカ人、イギリス人、オーストラリア人などが日本人の生徒に英語を喋るときに、だんだん、それぞれの祖国に特有ななまりなどがとれてきて、同じような英語になるということです。そして、吉田先生は、そのことを、「美しい」ことだとおっしゃっています(14分めあたり)。
おそらくビジネスイングリッシュでも、同じことです。
結論や理由、感想、感情、状況分析、意図などを相手にコミュニケーションするのですから、問題はその内容です。必ずしもネイティブの英語そのものを自分が話さなくてはならない、という強迫観念を持つ必要はないのです。
しかし、このような「インターナショナルイングリッシュ」の提唱に対しては、 やはりネイティブ並みでないと本当は相手にされないのだ、とか、幼児に話すように英語をネイティブに話しかけられても意味がない、という反対意見もあります。
私は、ネイティブ社会の一員になり日本人のアイディンティティを捨てる境遇ではないかぎり、Traveler's eyeは日本人として持ち続けざるを得ないと思います。それなら、言葉もネイティブ「並み」である必要はまったくありません。コミュニケーションが相手を理解することと定義するなら(相手と同化するという意味ではなく)インド人の英語も英語としてコミュニケーションが立派にできているし、日本人の英語も同じです。国際的に通じ合える英語であれば、コミュニケーションのツールとしては必要十二分と考えます。その意味で、吉田教授の考えに、私は賛成です。
そして、私は、さらに「状況対応型」英語ともいうべき、英語の使い方の習得(簡単な英語の適材適所の使い方のa-ha体験のこと)こそが、日本人の「インターナショナルイングリッシュ」習得への一番実効性のある近道だ、と考えています。