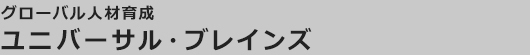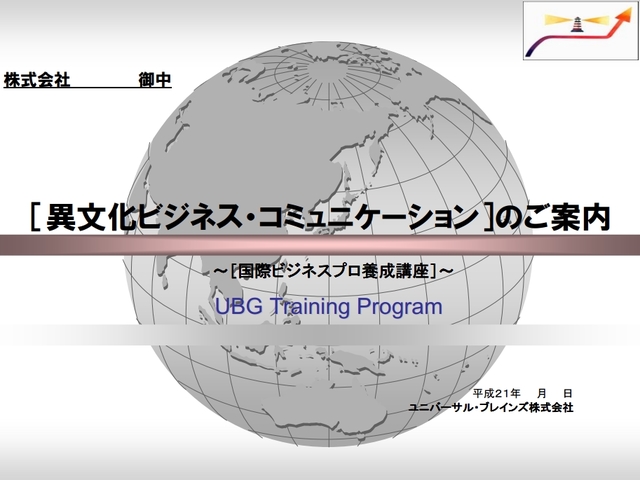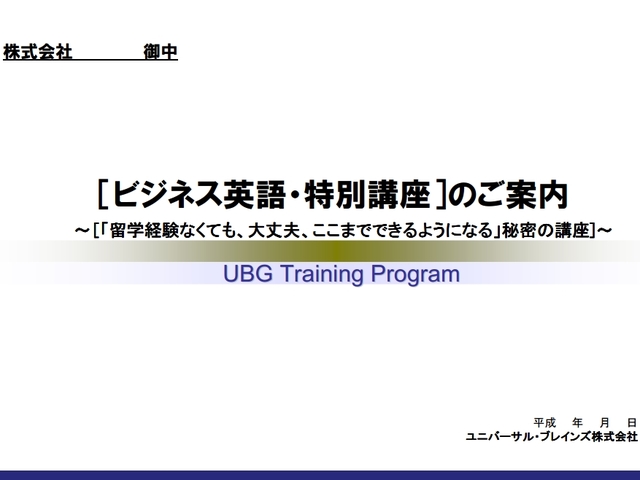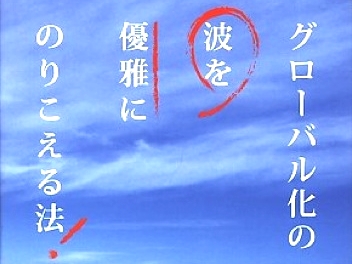「グローバル人材育成」のポイントについて
ドラッカー教授はビジネスのグローバル化に関して次のような言葉を残しています。
“経営戦略の基本が変わった。いかなる組織といえども、リーダー的な組織が設定する事実上の基準に達しないかぎり、成功はもちろん、生き残ることさえおぼつかなくなった。いかに事業と市場がローカルであろうとも、情報伝達の容易さと迅速さゆえに、あらゆる組織がグローバルな競争力を必要とするようになった。”
出典:P.F.ドラッカー「明日を支配するもの」
今やビジネスの世界においても国境は限りなく無くなってきているのです。
このようなビジネスのグローバル化を踏まえて、楽天は公用語を英語に変更しましたし、ユニクロは全店長を海外に派遣するという制度を導入しました。
また、武田薬品工業は新卒採用の際にTOEIC730点以上という条件を課しました。
私達個人が好むと好まざるとにかかわらず、これからのビジネスパーソンはグローバルな視点から物事を考えることができなければ、ビジネスチャンスをものにすることは限りなく難しくなってくるということです。
「グローバルに考え、ローカルに行動する」必要があるのです。
この「グローバルに考え、ローカルに行動する」姿勢が、これからのビジネスパーソンに求められる非常に重要な資質になるといえるのではないでしょうか。
しかし、キャッチフレーズとして「グローバルに考え、ローカルに行動する」必要があるとはいえ、具体的にどのようにマインドセットを変えていったらいいのでしょうか。
日本は島国なので、従来からグローバルという視点で物事を考える機会が少なく、ある意味仕方のないことかもしれませんが、これからはガラパゴス的な考えでは世界経済から取り残されることは避けられません。
TOEICの点数を730点以上とれば、「グローバルに考え、ローカルに行動する」ことになるのでしょうか。
いいえ、それだけでは、「グローバルに考え、ローカルに行動する」ことの自動達成はできないのです。
実際は、考え方のフレームワークの転換が必要です。
それを異文化コミュニケーションの視点から構成することこそ、「グローバル人材育成」の要といえます。
実際、前述の武田薬品についてもスイス医薬品大手ナイコメッドを一兆円を超える資金で買収する報道があります(毎日新聞2011年5月12日)。
この場合も、まさに経営の視点から、異文化コミュニケーションのスキルで問題解決していく、マインドセットの方向転換が求められている場面だと思います。